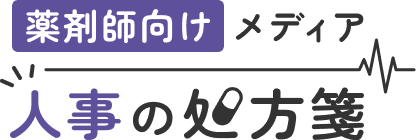
ホーム
- 薬剤師 人事向け記事一覧
- 教育の最終目標は学んだ研修の「アウトプット」
教育の最終目標は学んだ研修の「アウトプット」
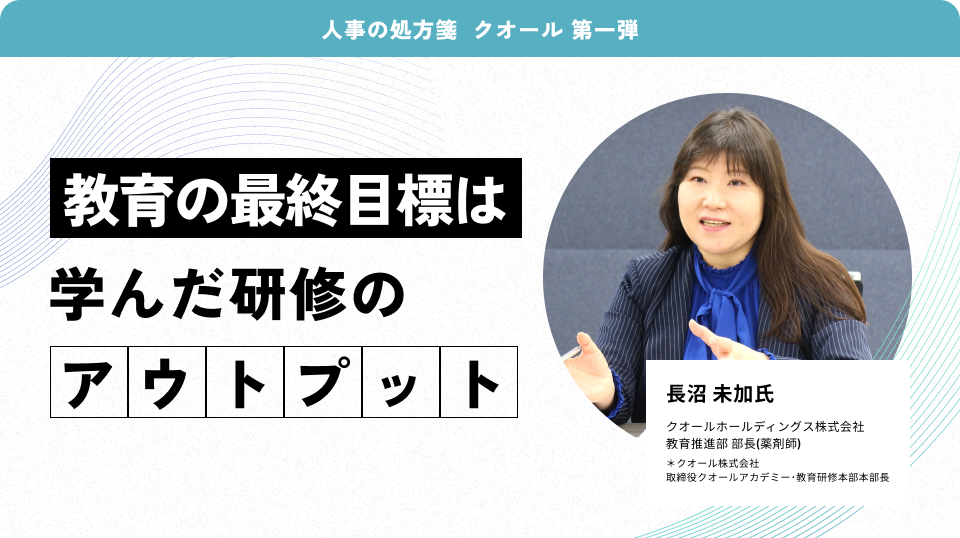

クオールホールディングス株式会社
教育推進部 部長(薬剤師)
長沼 未加 氏
*クオール株式会社 取締役クオールアカデミー・教育研修本部本部長
前任者の仕事内容を慣習のように引き継いでいた管理薬剤師の業務見直しが、教育研修に深く関わる端緒となりました。2024年4月にクオールホールディングスの教育推進部部長に就任した長沼未加氏は、社員一人ひとりが自発的に考え行動に移す力を醸成することで、「自走」できる人財の育成に注力しています。単なる研修資材作成のための教育担当部門であってはならないと戒めながら、研修で身に付けたことを現場でいかに「アウトプット」できるかが、教育研修の最終目標と強調します。傘下の事業会社が拡大する中で、中核事業会社のクオールを中心とした教育研修プログラムの「横展開」も課題です。ホールディングスの教育推進部部長という新たなポジションで事業会社の教育担当者の連携を強化し、教育研修の均てん化が進みます。
「慣習」で対応していた管理薬剤師業務に危機感
2002年にクオールに入社し2012年に教育研修部に異動するまで、二つの薬局で管理薬剤師や薬局長を経験しました。当時の旗艦店だった恵比寿店での特定共同指導は、私自身が教育研修のあり方を考える上で「原点」となるような出来事でした。
特定共同指導とは、保険診療が適正に行われているかどうかを確認するため、厚生労働省が主体となって都道府県と共同で実施する個別指導の一種です。当時のジェネリック医薬品に関する切り替えの流れを中心に、受付から服薬指導までの個別面接が行われ、各患者の薬歴に基づいた個別指導にも対応しました。そうした行政指導を受ける中で、管理薬剤師の業務を「慣習」でやっていることに気付かされたのです。薬大・薬学部を出て薬局薬剤師になった。管理薬剤師として勤務したけれど薬局の管理薬剤師たるもの何をやらなければならないのか、何が法規で決められていて何を管理しなければならないのかを考えるような文化はなく、今までの仕事を踏襲する、「慣習」のようなものが何となく残っていることはないでしょうか。薬機法はじめ薬剤師法や健康保険法(療養担当規則や薬担規則)などで決められた理路整然としたルールに慣習で対応していた自身を省み、これは危険だ、危ないと率直に痛感しました。
そんな経緯もあって、2012年に教育研修部に異動になって一番最初に取り組んだのが、管理薬剤師の教育研修体系の構築です。管理薬剤師としての教育の重要性のほか、管理薬剤師の法的立場の理解と教育に尽力しました。
このルールが法的な根拠に基づくものなのか、あるいは企業独自のルールなのか、そうした区別を明確にしていく必要性も感じました。この業界では薬事コンプライアンスの遵守は絶対です。管理薬剤師になる前に知っておかなければならないこと、言わばプレ研修のようなものから、管理薬剤師になってからの資質向上のための継続研修に注力しました。その頃はまだ300店舗ほどの企業スケールだったかと思いますが、一薬局には管理薬剤師が一人いるわけです。その人たちを守りたい。守るためには教育研修体系を構築しなければ、との思いが強くありました。

ディスカッションに時間割く研修でアウトプット後押し
理想としているのは「アウトプット」ができるような教育研修です。研修で身に付けたことを現場でどれだけアウトプットできるかが、教育研修の最終目標と位置付けています。そのためには長期のスパンで研修内容を自分自身のものにしてもらうことが必要と考えています。現在当社では、対人業務に必要な薬学管理スキルを醸成するため6年間にわたる教育プログラムを導入し、基礎から段階的に医療チームの一員として高度専門性を備えた薬剤師の育成を行っていますが、単発ではなく一つの研修テーマごとに3~4カ月の期間をかけているのが特徴です。
一堂に会しての研修スタイルだと、なんでもかでもそこに詰め込みたくなるものです。ところがそれだと全てを覚えるのが難しい。つまり、結果としてアウトプットが十分にできないことになる。コロナ禍を経て、集合研修は完全オンラインやハイブリッド型が主流となりました。集合研修はウェブでいいのではないか。むしろ皆を集める研修では、ディスカッションやロールプレイングに費やす時間のウエイトを高めたほうがよいと考えています。議論や疑似体験があるからこそ、様々な答えや気付きがあって自分自身の印象や記憶として残る。それを現場に戻った際の知識として活かす。つまり「アウトプット」ができるわけです。
そのためには参加者一人ひとりの事前学習が大切になってきます。事前学習とはいえ、もちろん研修の一環ですから業務時間内に行うものですが、個々の事情に合わせたフレキシブルな取り組みができるのは、eラーニングやオンライン研修のメリットと考えています。
正直に言えば事前学習が十分でないケースもあります。手本となるような姿勢を見せれば気付いてくれることもありますが、やはり言葉にしないと伝わらないこともある。手間のかかるスタッフには教育担当者がしっかりと手間をかけることが必要になってきます。薬剤師資格は生涯ライセンスです。自分自身の成長のため自覚と意識を醸成することは、ものすごく大事なことです。一人も取りこぼしたくはない。教育研修にはそんな気持ちで臨んでいます。
また、6年間にわたる年次研修では「リフレクション」(=振り返り)を重視しています。社会人として「なりたい自分」に向けた行動ができているのかどうか、それを再確認する機会を折に触れて提供しています。
自前の研修資材作成避け良質な既存資料を活用
教育研修では薬剤師としての専門性醸成に加え、社会人基礎教育となる「人財育成研修」にも力を入れています。局内だけでなく局外でのチームワークの重要性が高まる中、自ら考え行動できる「自立型」人財、正しい知識で正しい行動ができる「問題解決型」の人財育成を目指しています。言わば「自走」できる人財の育成です。
大きく方向転換するきっかけとなったのは、2009年4月に公表された日本薬剤師会の「薬剤師に求められるプロフェショナルスタンダード(PS)」です。当時の研修内容にPSを当てはめてみると、ともすれば薬物治療の知識などに偏重しがちで、医療倫理や生命倫理、生涯研鑽の意識などの分野に弱みがあることに気付きました。全てを反映させることまではできませんでしたが、これを機会に教育内容を刷新しました。
教育研修システムを構築する上で陥りやすいのは、自ら研修資材などの必要資料を一から作り始めてしまうことです。これをやってしまうと、どうにもならなくなることがよくあります。大事なのは、伝え方や理解のしやすさなど研修における個々の多様性を重視し、一律ではない多様な学習方法を効果的に提供していくこと。そして教育担当者が教育方針のレールを敷き、すでにある多様な良質の研修資材の中から自社の教育研修に相応しいものがあれば選択し活用することです。
以前の学習方法は、「これができるようになるため」のトレーニングでした。このフィーを算定したいから、そのためのノウハウを会得するという短絡的な研修がその典型です。戦略的に教育企画をし人財を育成してこその企業教育では、例えば単にガイドラインを閲読するだけではなく、ガイドラインを読み解く能力に論文ならびにエビデンスを引用する能力、さらには判断能力を醸成することが求められてきます。それが「自走」できる人財の育成へとつながります。

事業会社担当者との「顔の見える関係」強化
傘下企業は中核会社のクオールを含め19社にまで拡大しています。教育研修はホールディングスからの委託を受けクオールが担うという体裁になっており、クオールの教育研修本部と各社の教育リーダーが連携して展開しています。私自身がクオールの教育研修本部長とホールディングスの教育推進部長を兼務することになったことで、さらに動きやすくなりました。
「教育」は各社にとっての共通言語ではありますが、やはり「顔の見える関係」づくりは大切です。1カ月に一度の頻度で各事業会社の教育担当者による会議を開き、課題の共有や情報交換などを行っています。
教育効果の“見える化”は大切なことですが、その一方では薬局や薬剤師の医療貢献の見える化も必要だと思っています。医療費の削減に貢献したとか安全性向上に寄与したとか、そこはもっと見える化しないとラインセンスがもったいない。一生懸命やっているから患者さんから感謝されている「らしい」では、残念じゃないですか。教育の側面からもしっかりと後押しして、エビデンスを創出することができれば、と尽力しています。