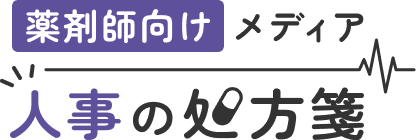
ホーム
- 薬剤師 人事向け記事一覧
- 薬局は週44時間労働がOK?特例措置対象事業場のルールと注意点
薬局は週44時間労働がOK?特例措置対象事業場のルールと注意点
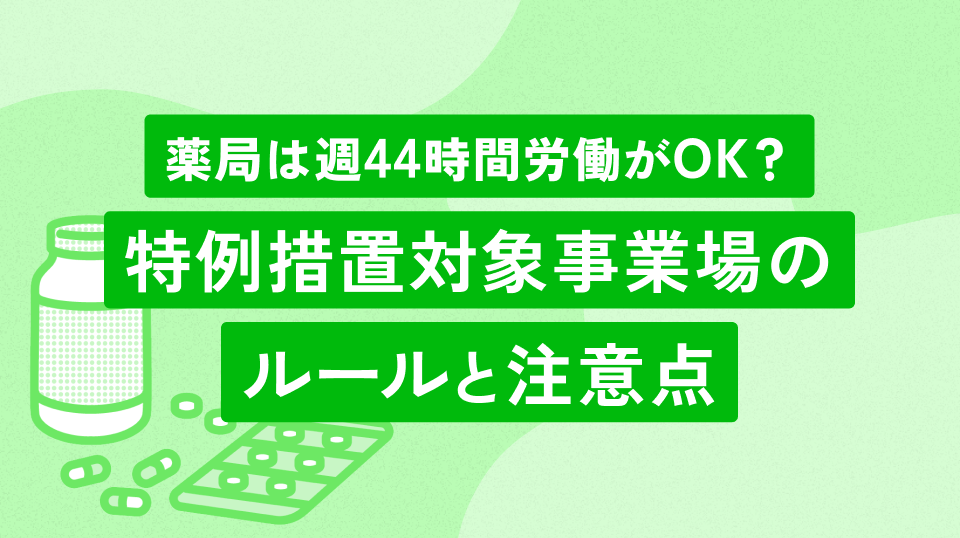
多くの薬剤師が働いている薬局やドラックストアでは、週44時間の労働が可能な場合があることをご存じでしょうか。
労働基準法では原則として週40時間が上限とされていますが、一定の条件を満たす事業場は「特例措置対象事業場」として週44時間までの労働が認められています。
本記事では、薬局やドラックストアがこの特例措置の対象となる条件や具体的な労働時間の設定方法、注意点について解説します。
特例措置対象事業場とは?
特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を雇用する以下の業種に該当する事業場のことです。
- 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、薬局、ドラッグストア、その他の商業)
- 映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業)
- 保険衛生業( 病院、診療所、社会福祉施設、その他の保健衛生業)
- 接客娯楽業( 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園、遊園地、その他の接客娯楽業)
特例措置対象事業場に該当する会社では、法定労働時間を週44時間とすることが認められています。
なお、事業場とは企業全体の規模ではなく、工場や支店、営業所等の個々の事業場単位の規模をいいます。薬局の店舗もそれに該当します。
徳島労働局「法定労働時間」
常時10人未満とは
「常時10人未満」とは、個々の事業場単位で常態として10人未満の従業員を雇用しているという意味です。正社員だけではなく、契約社員やパートタイマーなどの名称にかかわらず、以下のいずれかに該当する従業員を指します。
- 期間の定めなく雇用されている人
- 過去1年以上引き続き雇用されている人
- 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人
たとえば、週3日の勤務をするパートタイマーの薬剤師を雇用していたとしても、1年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は「常時雇用する従業員」に該当します。
なお、常時10人以上の従業員を雇用している事業場で、一時的に10人未満となったとしても、特例措置対象事業場の適用はされません。
診療所や薬局・ドラックストアは特例措置対象事業場に該当する
薬局やドラックストアは、小売業(医薬品・化粧品小売業)に該当するため、特例措置対象事業場に該当します。そのため、薬剤師や医療事務などの従業員が常時10人未満である薬局やドラックストアは、週44時間までが法定労働時間となります。
事業場単位での従業員数によって適用の可否が決まるため、個別の状況をよく確認することが大切です。
特例措置対象事業場の適用条件
特例措置対象事業場として週44時間の労働時間を適用する際は、行政への届出は不要です。
ただし、週44時間の労働時間を従業員に適用するには、就業規則と雇用契約書の見直しが必要となる場合があります。週44時間の労働時間が認められる場合であっても、就業規則や雇用契約書が週40時間を所定労働時間として定めている場合は、所定労働時間を超えた分の残業代の支払いが発生するため、注意が必要です。
就業規則と雇用契約書の記載例は以下のとおりです。
【就業規則の記載例】
第〇条(所定労働時間)
1 所定労働時間は1週間44時間、月曜日から金曜日は1日8時間、土曜日は4時間とする
2 各自の始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする
月曜日から金曜日
始業時刻 8時30分
終業時刻 17時30分
休憩 12時から13時
土曜日
始業時刻 8時30分
終業時刻 12時30分
【雇用契約書の記載例】
始業・終業時刻: 月曜日~金曜日:8:30~17:30(休憩1時間)・土曜日: 8:30~12:30
所定労働時間: 1日8時間(土曜のみ4時間)・週44時間(特例措置対象事業場のため)
詳細は就業規則第〇条
特例措置対象事業場の薬局における事例
特例措置対象事業場が適用される薬局では、以下の勤務形態が考えられます。
- 土曜日を4時間にする
- 1日の労働時間を7時間20分にする
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を併用する
土曜日を4時間にする
特例措置対象事業場では、週44時間の労働時間が認められているため、月曜日から金曜日の平日5日間を8時間勤務、土曜日を4時間とする週6日勤務にすることが可能です。土曜日の午前中のみ営業する薬局などにとって、実務に即した運用が可能になります。
ただし、特例措置対象事業場において延長が認められるのは「週」の法定労働時間であり、「日」あたりの法定労働時間の上限は8時間である点に留意する必要があります。そのため、仮に1日8時間を超えて勤務する場合は、時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。
1日当たりの労働時間を7時間20分に設定する
各勤務日の労働時間を均一にしたい場合は、月曜日から土曜日の6日間をそれぞれ7時間20分とする方法があります。
労働時間を均一にした場合は、週の労働時間を合計44時間としつつ、1日あたりの勤務時間をほぼ均等に配分できます。1日の労働時間に大きなばらつきがなくなり、週休2日制を採用しなくても運用が可能になります。無休で営業している薬局など、業務の実態に応じた柔軟なシフト管理がしやすくなるでしょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制を併用する
特例措置対象事業場では、1ヶ月単位の変形労働時間制を併用することも可能です。特例措置対象事業場では、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合でも1週間の平均労働時間を週44時間まで延長することが認められています。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月間の労働時間の平均を週40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)に収めることで、日ごとの労働時間について、を8時間を超えて変動できる制度です。
たとえば、インフルエンザなどの感染症が流行る繁忙期の労働時間を9時間に設定し、閑散期を7時間に設定するなど、業務の状況に応じた柔軟なシフト調整が可能になります。
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する際には、労使協定の締結や就業規則の整備などの手続きが必要となるため、事前の準備が必要です。
特例措置対象事業場の人事担当者が押さえるべきポイント
特例措置対象事業場では、通常の事業場とは異なる労働時間の上限が適用されるため、人事担当者は労務管理のポイントを押さえておく必要があります。
特に、残業代の計算基準や事業の規模変化に伴う適用条件の見直しなど、状況に応じた対応が求められます。誤った運用をすると、未払い残業代の発生や労働基準法違反につながる可能性があるため、制度の正しい理解が不可欠です。
残業代が発生する時間を押さえておく
特例措置対象事業場では、法定労働時間が週44時間とされていますが、1日の法定労働時間は8時間です。1日8時間または週44時間を超えた労働時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になります。
残業代の計算ルールを明確にし、適正な賃金支払いを徹底することが求められます。
事業の成長とともに適用条件が変わる可能性がある
特例措置対象事業場の適用条件の一つに「常時10人未満の労働者を使用していること」があるため、事業の成長とともに従業員数が増加すると適用対象外になる可能性があります。例えば、調剤薬局やドラッグストアでは、処方箋枚数の増加による薬剤師や医療事務の増員が考えられますね。
特例措置の適用外となった場合、法定労働時間は週40時間に変更され、時間外労働の基準も変わるため、就業規則や労働時間管理の見直しが必要になります。人事担当者は、従業員の増減に伴って適用条件が変わるタイミングを適切に把握し、早めに対応できるよう準備を進めることが大切です。
まとめ
特例措置対象事業場では、週44時間までの労働時間が認められるため、薬局やドラックストアにおいても柔軟な労働時間の設定が可能です。土曜日を短時間勤務とする方法や、1日当たりの労働時間を均等にする方法、さらには1ヶ月単位の変形労働時間制との併用など、さまざまな運用が考えられます。
しかし、1日の法定労働時間は8時間である点は変わらないため、超過した時間には時間外労働としての割増賃金が発生します。また、特例措置の適用には従業員数の条件があり、事業の成長に伴い適用外となる可能性もあります。人事担当者は制度の内容を正しく理解し、適用条件の変化にも柔軟に対応できるよう備えておくことが大切です。
