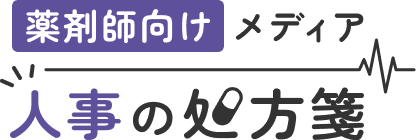
ホーム
- 薬剤師 人事向け記事一覧
- 赤羽根先生が解説!薬剤師採用における法的リスクと対策1
赤羽根先生が解説!薬剤師採用における法的リスクと対策1

編集部からのコメント
- このコーナーは薬剤師資格を持つ弁護士の赤羽根秀宜先生に、病院や薬局、ドラッグストアの採用や人事・労務に関するトラブルや気になる問題に回答いただくコーナーです。薬剤師の採用を担う人事担当者の方はもちろんのこと、薬剤師を雇用する経営者の方にも有益なコンテンツをお届けいたします。
質問1
掲載している求人に求職者から応募があったのですが、良い人が複数いたことから、当初予定していたよりも採用する人数が増えてしまいました。色々考え、内定後に何名かの方には別の条件でお願いできないか打診しました。そうすると「つり広告、詐欺広告」などの指摘を受けました。どの段階で掲載条件との違いを明示しなければならなかったでしょうか。
回答
企業等が労働者の募集を行う場合や公共職業安定所(ハローワーク)等に求人の申込みをする場合には賃金等の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法第5の3第1項、第2項)。虚偽の条件を提示して労働者の募集やハローワーク等への求人の申込みを行った場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(職業安定法第65条第1項第9号、第10号)。
そのため、求職者を集めるために最初から変更ありきで好条件を提示し、採用後に不利な条件で労働に従事させるような虚偽の条件に該当する場合には、「つり広告、詐欺広告」となり問題となります。一方、虚偽の条件を示したわけではない場合には、求人広告の条件がそのまま労働条件とならないからといって直ちに違法となるわけではありません。労働契約の際にご質問の場合のように労働条件を明示し求職者が納得して労働契約を締結すれば、変更後の内容で契約が成立するのが原則です。
ただし、労働条件の変更については、「明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。」(「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号))とされていますので、変更があり得る場合には明記する、変更した場合には速やかに知らせる必要があります。また、明示された条件と異なる条件での契約をする場合には、変更の内容の明示など労働者への配慮した対応も求められていますので注意が必要です。求人広告等の記載内容は、労働契約締結時にこれと異なる合意をするなどの特段の事情がない限り、労働契約の内容になると判断している裁判例もあります。
また、指針では、募集にかかる明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであるとし、安易な変更はしてはならないとされていますので、この点も注意を要するでしょう。
質問2
求職者から個人情報の消去を求められました。どのように対応したらいいでしょうか。
回答
個人情報保護法では、個人情報の保存期間や廃棄すべき時期について規定はしていませんが、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければならないという努力義務が個人情報取扱事業者には課されています(個人情報保護法第22条)。法的には努力義務であっても保有している以上は安全管理も求められますし、情報漏えい等のリスクもありますので、一定の時期を定めたうえでまとめて消去するなどの対応をしておくことが望ましいと考えます。
さて、ご質問は任意の消去ではなく、求職者から消去を求められた場合です。この場合には、募集の取得時に特定した利用目的が達成されている場合には削除が必要となります(個人情報保護法第35条第5項)。したがって、採用を目的としていれば採用が終了しているような場合には消去することが原則となるでしょう。
一方で利用目的が達成となっていない、不要となっていない場合等はどうでしょうか。この場合は法的な根拠が認められた場合には消去に応じなければなりません。
消去しなければならない場合としては、個人データが利用目的の範囲外で利用されている場合や違法な行為にかかる利用がされているなど個人情報保護法の定めに反して取り扱われている場合又は個人情報保護法に違反して不正に取得された場合があります(個人情報保護法第35条第1項)。
また、個人保護法第26条第1項本文に規定する事態が生じた場合(要配慮個人情報や財産的被害が生じる可能性のある情報の漏えい等が生じた場合等)、その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合も消去が必要です(個人情報保護法第35条第5項)
なお、本人からの消去などの利用停止等の請求がなされた場合、その請求に理由があることが判明したときは、原則として、遅滞なく、当該保有個人データの一部または全部の利用停止等の措置を行わなければなりませんし、対応しない場合には本人に通知が必要となります。
このような請求に関して、法令に従って誰がどのように対応するか、流れを決めておくとよいでしょう。

薬学部卒業後、薬剤師としての勤務経験を経てから弁護士に。薬剤師としての知識・勤務経験及びネットワーク等も活用し、薬事・ヘルスケア・医療等に関する事業等の法的支援を取り扱う。