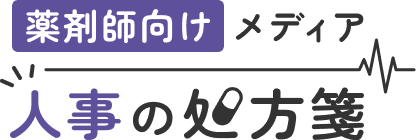
ホーム
- 薬剤師 人事向け記事一覧
- 【薬局・病院人事向け】産前・産後・育児休業の実務ガイド
【薬局・病院人事向け】産前・産後・育児休業の実務ガイド

この記事では従業員が産前・産後休業や育児休業を取得したいといった場合、人事担当者としてどう対応するべきかについて解説します。病院や薬局というのは、基本的には余剰人員を抱えていることろはあまりありません。
出産や出産後の復職を機に、社員が退職を選ぶことのないよう、社内フローをしっかりと整えておきましょう。
産前・産後・育児休業とは?
産前・産後休業とは、労働基準法の母体保護規定に基づく休業制度です。産前休業については取得するかどうかは、本人の希望によりますが、希望した場合は就業させることはできません。休業期間は、出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合は、その差の日数分も産前休業に含まれます。
産後休業に関しては、本人の意思に関係なく就業させることは禁止とされています。休業期間は8週間ですが、産後6週間が経過し本人が就業を希望し、医師が認めた場合は就労可能です。なお、産後休業の出産は、妊娠4ヵ月以上の分娩のことをいい、「生産」だけでなく、「死産」や「流産」「早産」「人工妊娠中絶」も含みます。
育児休業とは、育児介護休業法に定められた両立支援制度で、子が1歳(最長2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間)は、申出により育児休業の取得することができます。
取得期間
産前休業:出産予定日の 6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産日まで
※労働者が請求した場合、就業させてはならない期間
産後休業:出産日の翌日から 8週間
※基本的には就業不可。ただし産後6週間を経過し、本人が就業を希望し、医師が認めた場合は就労可能。
育児休業:子が1歳(最長2歳)に達するまで。保育園に入園できない場合は、申請の上、延長を行う。
※パパ・ママ育休プラス:父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間
対象者
産前・産後休業:雇用形態に関係なく、すべての女性労働者(パート・契約社員・派遣含む)が対象。
育児休業:原則として1歳に満たない子を養育する従業員
※パートタイマーや、1日の労働時間が通常より短い方であっても、 期間の定めのない労働契約によって働いている場合は育児休業可能です。
番外編:時短勤務制度とは?
時短勤務制度とは、仕事と育児・介護の両立を目指すため、育児介護休業法によって定められた制度です。3歳未満の子供を養育する従業員は1日の労働時間を5時間45分~6時間にすることが義務化されています。もし、時短勤務をするための要件を満たした労働者から申し出があった場合には、その申し出を拒否することは基本的に違法となります。3歳以降に関しては、時短勤務の対象からは外れてしまいますが、企業は従業員が時短勤務を続けられるよう努力義務があるとされています。
2025年4月1日から育児・介護休業法が改正されたことにより、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
選択して講ずべき措置
1:始業時刻等の変更
2:テレワーク等(10日以上/月)
3:保育施設の設置運営等
4:就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5:短時間勤務制度
※2と4は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
※事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
多くの病院や薬局では、時短勤務は3歳未満(子の3歳の誕生日の前日)までとされていますが、3歳になったからといって子供の手がかからなくなるわけではありません。薬剤師という仕事の特質上、家庭とのバランスが取れないとなると転職してパート勤務になったり、子供が小学校低学年までは専業主婦になるということを選択したりする方は意外といらっしゃいます。人手不足の昨今を考えると、少しでも従業員の働きやすさを考えて制度をつくることが大切です。
人事担当者がやるべき対応とは?
皆さんの病院や薬局では、産前・産後休業、育児休業希望の従業員がいた場合のフローは整っていますか?すでに、フローが整っていたとしても、念のため確認をしておきましょう。
産前・産後休暇、育児休業について従業員に説明
産前・産後休業、育児休業はどんな制度なのかを従業員に説明しましょう。また、産前・産後休業、育児休業を取得する際に提出が必要な書類なども説明してください。
2022年より、出生時育児休業(産後パパ育休)が新設され、子の出生後8週間以内に4週間まで夫側も育児休業を取得できるようになりました。さらに夫婦共に育児休業を取得した場合は、パパ・ママ育休プラスが適用され、子どもが1歳2カ月になるまで延長して休業を取得できるようになっています。
昨今、育児・介護休業法が頻繁に改正されていますので、人事担当者として最新情報を把握し、正しい内容を従業員に伝えましょう。
提出書類の作成と提出期限の設定
「産前・産後休業」の取得に関する書類を作成し、従業員に提出してもらう必要があります。出産予定日の記載をはじめ、産前休業の取得希望の記載、産後休業予定日などを記載します。
なぜこの書類が必要かというと、社内の手続きだけでなく、事業主が日本年金機構に保険料の免除申請(事業主・従業員共に)を行う必要があるからです。
保険料の免除申請である「産前・産後休業取得者申出書」の提出期間は、産前・産後休業期間中または産前・産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内です。この書類の提出が間に合うように、従業員からいつまで申し出をしてもらう必要があるかを決めておきましょう。
そして、育児休業も産前・産後休業と同様に、提出書類の作成と提出期限の設定日を決めましょう。育児休業も、産前・産後休業と同様に保険料の免除対象となるため、事業主は「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。
店舗や薬剤部の人員の補充を考える
従業員の産前・産後休業、育児休業の取得がわかったら、休業期間の薬剤師の補充をどうするか考えましょう。特に対象の従業員が管理薬剤師の場合は、早急に別の管理薬剤師候補を探す必要があります。妊娠中は様々なトラブルが考えられ、急なお休みや長期的な不在も考えられます。報告を受けたら、なるべく早めに新しい管理薬剤師を立てることが望ましいでしょう。
人員に余裕のある病院や薬局の場合は、店舗異動等で人員の補充が考えられますが、できない場合は、派遣薬剤師に来てもらうなど対策を考える必要があります。
そして同時に、休業明けの対応も考えなくてはなりません。休業明けの1年~2年の間は、従業員は子供の発熱などで急なお休みをとることもあると思います。休みを取ることに引け目を感じ、そのまま退職をする薬剤師さんも少なくありませんので、従業員が働きやすい環境を作れるように、長期的な人員配置を考えておきましょう。
産前・産後休業と育児休業中~復帰後にもらえる給付手当金はいくら?
従業員の多くは産前・産後休業、育児休業中~復帰後にもらえる給付手当金に関しては把握できていないはずです。人事担当者が詳細を伝えることで、出産の不安や出産後の不安解消にもつながるので、説明をしておきましょう。
以下は全国健康保険協会の場合です。別の保険組合に加入している場合は、各保険組合のHPをご確認ください。保険組合によっては、各種手当金がさらにもらえる場合があります。
出産一時金
社会保険に加入している従業員は、出産一時金を受け取ることができます。受給額は1児につき一律50万円です。(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)直接支払制度(医療機関が申請・受取)と受取代理制度(医療機関が代理受取)、直接申請(出産後に自身で申請)と3つの方法があります。
出産手当金
出産手当金とは、女性従業員が出産のために休んでいた期間、生活費の一部として支払われるお金です。出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象にしています。
【支給額】
1日当たり、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
出生時育児休業給付金
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支払われます。
【支給額】 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※育児休業給付金と同じ。
出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に支払われる給付金です。出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間されます。
【支給額】休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%
※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。
※2支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、 28日が上限。
参照:2025年4月から 「出生後休業支援給付金 」を創設します_厚生労働省
育児休業給付金
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した従業員に支払われる給付金です。
【支給額】休業開始時賃金日額※1×支給日数※2×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」
※1休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6ヵ月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2育児休業給付金における1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。
育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
【支給額】育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
参照:2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します_厚生労働省
薬剤師は資格ありきのため、退職者も多数!トラブルに注意!
薬剤師の7割は女性。しかも資格ありきの仕事であるため、出産後に育休を最大限取得し、そのまま退職するケースは少なくありません。また、復帰したとしても子供の体調不良等による欠勤が続くことで引け目を感じ、退職をしてしまうケースもあります。その他にも様々なトラブルが想定されるので、問題が起きないように注意をしましょう。
起こりやすいトラブル
・育休後の配属先が希望と異なりトラブルに発展
・育児時短勤務の制度が整っておらず、復帰を断念
・薬局長と本部・人事の認識にズレがあり対応が後手に回り、会社に不信感が生まれる
・書類や制度の説明不足がにより、従業員に不利益が生じる
特に小規模な薬局や個人経営の薬局では、人事機能が十分でなく、制度の運用や説明が属人的になってしまっていることがあります。このようなトラブルを防ぐためには、制度の案内や申請書類の準備をマニュアル化し、全従業員に共通の対応ができる体制を整えておくことが重要です。
また、育休明けの復職プラン(時短勤務の希望や、配属店舗、担当業務など)については、休業中に1回は面談を実施するのが理想的です。本人の希望と会社側の受け入れ体制をすり合わせておくことで、不要な退職やトラブルを防ぐことができます。
人事担当者は、産休・育休制度の活用を促すだけでなく、働きやすさ・復職後の支援まで視野に入れた設計を行いましょう。